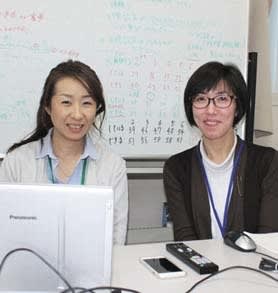北海道新聞1月14日付の記事は下記の通り。
![]()
函館市は1月13日、2016年度末で約32億円に上る見通しの函館、恵山、南茅部の3病院の累積赤字を半分程度に減らすため、緊急的に16年度一般会計から約15億円を病院事業会計に繰り入れる方針を決めた。緊急的な繰り入れは11年度の29億円以来、5年ぶり。病院事業会計の累積赤字が膨らみすぎると、病院の医療機器購入などで借金がしづらくなるためだ。
2月開会の定例市議会に関連の補正予算案を提出する。函館病院(668床)分として6億6千万円、恵山病院(60床)分で3億6千万円、南茅部病院(59床)分で4億7千万円を一般会計から繰り入れる。
市が同日発表した「病院事業改革プラン」素案に盛り込んだ。3病院の累積赤字は15年度末で19億9千万円で、わずか1年で1.6倍の32億円に膨らむ見通しとなったため、繰り入れを決めた。
市は11年度にも一般会計からの29億円の繰り入れで3病院の赤字額を大幅に圧縮した。しかし、その後も入院患者は伸びず、経営環境は好転していない。
市は、周辺に医療機関の少ない恵山、南茅部両病院の赤字については、来年度以降も一般会計から繰り入れを続けて、赤字解消を目指す方針。函館病院は繰り入れは行わず、自助努力による経営の健全化を図る。

函館市は1月13日、2016年度末で約32億円に上る見通しの函館、恵山、南茅部の3病院の累積赤字を半分程度に減らすため、緊急的に16年度一般会計から約15億円を病院事業会計に繰り入れる方針を決めた。緊急的な繰り入れは11年度の29億円以来、5年ぶり。病院事業会計の累積赤字が膨らみすぎると、病院の医療機器購入などで借金がしづらくなるためだ。
2月開会の定例市議会に関連の補正予算案を提出する。函館病院(668床)分として6億6千万円、恵山病院(60床)分で3億6千万円、南茅部病院(59床)分で4億7千万円を一般会計から繰り入れる。
市が同日発表した「病院事業改革プラン」素案に盛り込んだ。3病院の累積赤字は15年度末で19億9千万円で、わずか1年で1.6倍の32億円に膨らむ見通しとなったため、繰り入れを決めた。
市は11年度にも一般会計からの29億円の繰り入れで3病院の赤字額を大幅に圧縮した。しかし、その後も入院患者は伸びず、経営環境は好転していない。
市は、周辺に医療機関の少ない恵山、南茅部両病院の赤字については、来年度以降も一般会計から繰り入れを続けて、赤字解消を目指す方針。函館病院は繰り入れは行わず、自助努力による経営の健全化を図る。